南城 凛(みじょう りん)です。
今宵も凛のりんりんらいぶらり~にようこそお越しくださり、ありがとうございます。
凛とご一緒にどうぞおくつろぎくださいませ~(^-^)
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
世界中で新型コロナウィルスの影響が続いています。
日本国内では、豪雨で被害に遭われた方もいらっしゃいます。
あなたの生活には変化が生じていらっしゃいませんか。
くれぐれもお身体の管理にはご留意くださいますように。
自粛は解除になりましたが、雨のため、おうちで過ごすことが増えた方も多いのではないでしょうか。
退屈などと感じるのはいかがなものでしょう。
自分と向き合える時間にいたしましょう。
あなたにも、凛にも、与えられた時間は同じ一日24時間。
凛はこれまでと変わらず本とふれあう時間を大切にしています。
本から多くの事柄を学び、考え、そして、時空の旅を楽しんでいます。(^o^)
凛は、どうしたら不安を払拭して、未来に立ち向かう勇気が得られるかを考えてみました。
古代の日本の人たちはどうやって困難を乗り越えてきたのでしょうか。
そこで、日本の文字の始まりについて学び直して、原点に還ってみようと思いました。
何が原点であるかは、個々人の考え方や価値感が違うので、異なると思います。
あなたにとっての原点とは何でしょう。
さて、今回は古代の文学について、お勉強をいたしましょう。
え?寝る前に?と思われているあなた、ご心配要りませんよ。
お休み前のおくつろぎのひとときですので、さらりといきますね。
凛の机の棚にデーンと並べている蔵書から『改訂増補 最新国語便覧』(浜島書店、2009年改定版発行、2017年印刷・発行)を開いてみました。
オールカラーで、大人になっても「学んでいるぞ!」という気持ちになれます。(^^)v
この本の「上代の文学」の項、70頁~71頁には、「口承文学の発生」「文化の伝来」「記載文学」の三つの項目が掲載されています。
「上代」というのは、大和政権が成立する以前の多くの小国が分立した頃から、桓武天皇の平安京遷都(794年)までの時代をいいます。
では、簡単におさらいをいたしましょう。
まず、70頁には、「口承文学の発生」が掲載されています。
古代人にとって、自然の神さまたちと密接なため神事が発達したことから、文学の発生になる基盤が始まったとされています。
言霊信仰から、呪詞(じゅし)が生まれました。
まだ文字がない時代でしたから、歌謡だけでなく、人々の口から語り継がれていった神話や説話が生まれました。
これらは口承文学といわれます。
次に、「文化の伝来」(70頁~71頁)にいきましょう。
遣隋使と遣唐使の派遣によって、大陸からの文化の影響を受けて、飛鳥文化・白鳳文化・天平文化などが栄えました。
6世紀半ばごろに、大陸から仏教が伝来したと推定されています。
この項で凛が注目したのが、5世紀頃に、大陸から漢字と漢籍が伝来していたと推定されていることです。
外国語であったものを、漢字の音に日本語の意味をあてはめて訓とし、工夫されました。
漢字の音から「万葉仮名」や「宣命(せんみょう)書き」などが発明されたということです。
なんとすばらしい発明でしょう!\(^o^)/
これらの先人たちによる努力がなければ、あなたも凛も日本語で書かれた本を読むことができないのです。
最後に、「記載文学」(71頁)の項に入ります。
日本に文字ができたことにより、口から伝わる口承文学から、記載文学へと時代が推移します。
8世紀初頭、『古事記』『日本書紀』『風土記』などの優れた文学が生まれました。
751年に編まれた『懐風藻』は、現存する最古の漢詩集です。
そして、令和になり、今の時代を生きる私たちに、その存在をあらためて国民に知らしめた『万葉集』は、760年前後に成立されたとされる、現存する日本で最古の和歌集です。
以上、まとめますと、「上代の文学」は、「まことの文学」と呼ばれて、素朴な古代人の姿が表われていることが特徴とされています。(71頁参照)
ここで、凛のおさらいは終わりますよ~
凛にお付き合いくださり、ありがとうございました。
お疲れさまでした。
「上代の文学」にご興味を抱かれたあなたは、専門書でさらに詳しく学んでくださいね。(^-^)
まだ凛のブログは終わりませんよ~
ここで閉じないでくださいね。(^o^)
さて、大陸から漢字や漢籍が伝来して日本の文字文化が生まれたといわれていますが、それは、凛が上記でごく数行にしかまとめていない「上代の文学」の中のほんのわずかな部分でしかありません。
このごくわずかな文字数の中に、人々の壮大な歴史ロマンがあるのです。
今夜は、日本の文字の伝来・伝承という黎明期において、一族九代に渡って通訳として大活躍した物語をご紹介いたしましょう。
箒木蓬生(ははきぎ ほうせい)氏の長篇小説『日御子(ひみこ、上・下巻)』(講談社文庫、2014年)です。
2012年、講談社より単行本として刊行されています。
この作品の中心となる<あずみ>の一族は、中国と日本とを結ぶ使譯(しえき)という通訳を務める役目を代々受け継いでいきます。
言葉を媒介にして、大陸との外交を担っている<あずみ>一族には、代々伝わる四つの教えがありました。
凛が持っている文庫本初版の上巻の帯には、その四つの教えが紹介されています。
「人を裏切らない。─」
「人を恨まず、戦いを挑まない。─」
「良い習慣は才能を超える。─」
「骨休めは仕事と仕事の転換にある。─」
文庫本の上巻を開くと、まず「2~3世紀頃 倭国想像図」(4頁)が掲載されています。
那国、伊都国、弥摩大国、求奈国、壱岐国など、現在の北部九州の福岡県、熊本県、佐賀県、長崎県であることがわかるようになっています。
箒木蓬生氏は福岡県のご出身で、畿内説などの邪馬台国における様々な論争には触れずに、九州を舞台にした歴史ロマンの物語として描いていらっしゃいます。
この小説は三部構成となっています。
文庫本上巻の第一部は、「朝貢」で、<あずみ>一族の針が、祖父の灰から漢への使者となった体験談を告げられた話から始まります。
文庫本下巻からの第二部は、「日の御子」として弥摩大国の日御子女王に仕える炎女が中心となり、女王の不思議な力に魅せられます。
同巻第三部の「魏使」では、銘が、265年に建国された晋への使者となって大陸へ向かいます。
以上、三部の構成によって、灰、圧、針、江女、朱、炎女、在、銘、治の九代にいたる<あずみ>一族の200年に及ぶ壮大な歴史物語が展開されます。
第一部の祖父の灰が孫の針に語る体験談は、これから始まる歴史のうねりが予感されます。
何よりも那国の使者・灰が謁見した漢の光武帝に授かった「漢委奴国王印」である金印が出てくるところから、歴史上に物語るミステリー・ロマンとしてどんどん上書きされていき、読者の想像力が大いにかきたてられます。
<あずみ>一族は、先進国の漢から鉄や馬車や紙などの技術と文化を日本に伝えようと大変な努力をします。
<あずみ>の先祖が書き残した竹簡の文字から記録という概念がどれだけ貴重であるかを読み取れます。
凛は、針が大陸に渡っていく様子から、周辺国の海路と陸路が充実していたことに感動しました。
また、四つの教えを信念として子孫に伝えていく姿に、一族代々の誇りをもっていることに感銘しました。
それから、生口(せいこう)と呼ばれた人たちの存在にも驚きをもちました。
日常的に日本語の文字の読み書きをしている凛は、この作品のおかげで古代を生きた人たちの誇りを受け継ぎ、感謝して、原点に還った思いをいたしました。
精神科医で作家の箒木蓬生氏のこの作品は、2012年、『週刊朝日』歴史・時代小説ベスト10の第2位☆彡になり、また、2013年、第2回歴史時代作家クラブ賞作品賞☆彡を受賞しています。
帚木蓬生氏は、開業医を続けながら、多くの作品をご執筆されていらっしゃいます。
小説『三たびの海峡』(新潮社、1992年、のち新潮文庫、1995年)で、1993年、第14回吉川栄治文学新人賞を受賞☆彡され、小説『閉鎖病棟』(新潮社、1994年、のち新潮文庫、1997年)では、1995年、第8回山本周五郎賞を受賞☆彡の他、書ききれないほどたくさんの受賞歴があります。
ここにあげた二作品は映画化されて、ご存じの方も多いでしょう。
近年では、小説『守教(上・下)』(新潮社、2017年、のち新潮文庫、2020年)で、2018年、第52回吉川栄治文学賞受賞☆彡、第24回中山義秀文学賞受賞☆彡をされています。
帚木蓬生氏からの贈り物、古代歴史ロマンをあなたもご堪能されてはいかがでしょう。
読後には、言葉の大切さを知り、爽快な気分になれましょう。
凛は、読書を楽しめていることにあらためて感謝の念をもつことができました。
そして、困難に打ち勝つ勇気をもって明日へ臨んでいきましょう。\(^o^)/
それでは、あなたもよい夢をごらんになられて下さいね。
最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。
今夜も凛からあなたにおすすめの作品でした。(^-^)
************

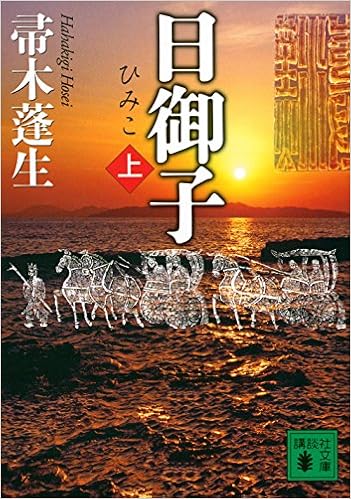
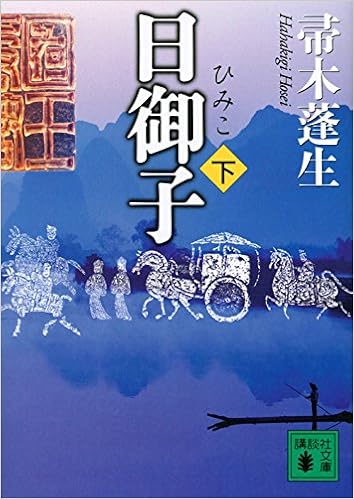
2 件のコメント:
お邪魔します。蒸し暑い天気が続きます。お変わりありませんか?私は元気でなんとかこの梅雨を乗り切れそうです。
先日車を走らせていると、数十センチに育った稲の中に、ゆるいS字状の杭のようなものが、あちらこちらにニョキッと立っていました。なんだろうと近づいて行くと、黄色い嘴が見えてきました。一面の早緑の稲田の中から、白鷺の首から上だけが覗いていたのです。今子育ての真っ最中なのでしょう、まだ毛の生え揃っていない灰色と白のまだらな子もいることに気付きました。それにしても最初見た時はかなりシュールな光景でした。
さて、ははきぎさんの『日御子』についてですが、私も日の御子(巫女)あるいは、姫巫女という考え方には賛成です。しかし、卑弥呼に関するイメージにかなり隔たりがあり、すんなり頭の中に入ってきませんでした。
筑後地方の水利に恵まれていない荒れ地に、灌漑を施し緑の沃野に変えた庄屋と農民たちの奮闘を描いた『水神』に感銘を受けました。
古代日本語を語る上で、次の三人は避けて通ることができないと思います。
言語学者の大野晋さん、『日本語をさかのぼる』『日本語はいかにして成立したか』など、積極果敢に新説を発表され続けました。私が知らないだけかもしれませんが、最近の文型の学者さんたちは優等生的になって、論議の的となるような新説奇説の発表が少ないと思います。
次は、漢字学者の白川静さん。甲骨文字や金文を詳細に研究され、漢字の語源の辞典とも言うべき『字統』をはじめとして4冊も個人で辞書を完成された唯一無二の方です。『初期万葉集』『後期万葉集』など素晴らしい著作です。
もう一人は古代文学者の西郷信綱さん。まさに碩学というイメージそのものの方です。隅々まで目配りの行き届いた著作ばかりです。『古事記注釈全8巻』『日本の古代を探る』『古代人と夢』『詩の発生』本当に凄い著作です。
さて、またまた長く語ってしまいました。次の配信を楽しみにしています。では。
Kohtaさん、こんばんは。
コメントありがとうございます。(^-^)
Kohtaさんのお住まいのお近くでは、稲が順調に育っているようですね。今年も豊作でありますように!
白鷺の子育てが見られるのですか。
親鳥たちが必死で育てているのでしょうね。このまま見守っていきましょう。
何よりも安全運転でお願いいたしますね。
想像力を膨らませて、いろいろな卑弥呼像があってよろしいのではないかと思います。
最近は弥生時代から遡って縄文時代への注目度が高まっていますね。
帚木蓬生氏の作品では『千日紅の恋人』(新潮社、2005年、新潮文庫、2008年)が好きです。
女性主人公に対する応援歌が物語の底に流れているようで、最後までとても楽しめました。
いつもご教示ありがとうございます!
古代日本語についてご興味のある方は、Kohtaさんにご紹介していただきました三人の先生方の本をお読みになられてくださいませ。
Kohtaさん、これからもよろしくお願いいたします。(^-^)
コメントを投稿